声の諸相 解説 その4

ただ、横に座って一緒にコーヒーを飲む。それだけで、言葉を使うよりも伝わるものは確実にある
【前回までのまとめ】
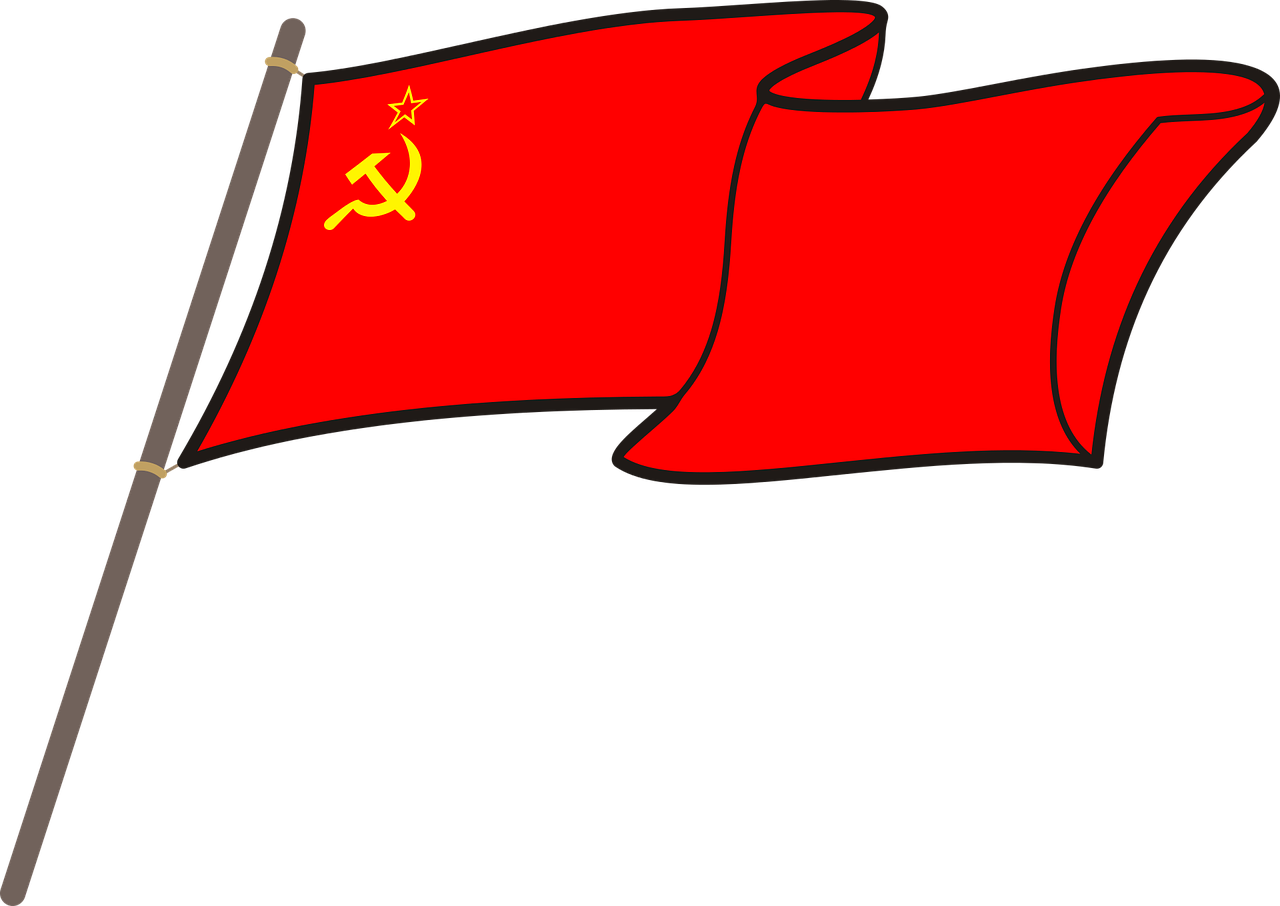
ソ連政権化で人々の破滅と矛盾を描いた、ドフトエフスキー
-饒舌よりも沈黙を良しとする筆者-
滑らかに喋ること。淀みなく説明できる力は、とても重要なものだと思われています。
けれど、同時にそれは人間らしくないとも言えるのです。
何故なら、人は元々何かしらの刺激があって初めて考えるし、思考の方が圧倒的に早く、膨大な情報処理を自分で無意識に行っています。言葉は、それに追いついていけないのです。
だから、滑らかな喋りができる人、というのはあらかじめ用意している。準備していることが前提となります。(良いスピーチは、必ず練習を積んでいると言いますし、演説や講義など、滑らかに説明することが求められている場は、練習を必ずしているのです。)
普通の会話で、答をあらかじめ用意している、というのは変ですよね。
そこに、人は違和感を抱き、どこかしっくりせず、不快感を覚えてしまう。
逆に、寡黙である。口べたの意味である、訥弁で有ることの価値を解いています。
何も用意せず、その場で伝えたいことの為に必死で言葉を探している。その必死さや、不器用さに、どうにも人は惹かれてしまう。
そこには、真実の心が介在しているからです。
-言葉は万能な道具ではない-
言いたいことが溢れているのに、どうして私たちは沈黙してしまうのか。
それは、感情の量や熱が圧倒的に言葉のそれよりも強い時、その衝動や感動をあらわすのに、この言葉しか無いのだけれども、それでは薄っぺらい。自分の感情の量についていけない。
もっと良い言葉はないだろうか。もっと相応しい言葉が無いのか。もっと適切表現は……と、言葉のもつ、程度の深さを示すことができない限界に触れた時、人は沈黙するしか無くなってくるのです。
言葉は、伝達の道具です。
けれど、道具には必ず限界が存在する。
その限界に触れ、けれども同時に伝えたい衝動が込み上げてきた時、人は黙るのです。
その衝動に突き動かされ、何かしらの出口を探そうとあえいでいる気配や態度が、私たちの心を揺らすものとなり、沈黙が最も表現力の強いものと成りえるのだという、筆者の主張と繋がっていきます。
では、ラストの部分を読んでみましょう。
【第5~6段落】
-古典小説から受け取れるもの-
ドフトエフスキーの小説の登場人物たちの多くからは、文章にそうしるされてはいなくとも、心の沸騰音や吸気音、訥音、気息の乱れを聞くことができる。(本文より)
ここで面白い表現が使われています。
小説を「読んで」いるのに、「聴くこと」ができる。
おかしいですよね。耳で「聴いて」いるものは何一つないはずです。けれども、その小説のなかに没頭し、人々の感情の動きや揺れ、躊躇いや嬉しさ、悲しみや葛藤を受け取ってしまうと、書いてない筈の行間に、きっと今、この登場人物は悲しみを耐えて、俯いて、何かを言い掛けているのを耐えているに違いない。
その、感情の重み。揺れは、容易く言葉に出来るものではない。
そんな、薄っぺらい物ではない。
この小説の登場人物たちは、そんな生半可なことに苦しんでいないし、その辛さの重みに読んでいる自分が引き込まれているからこそ、簡単に言葉に出来ないものを理解できるから、頭のなかでそう描いてしまうのです。
具体的な映像や、与えられた、具現化された世界。舞台や映画などでもそれを感じることはもちろん出来るし、上手く具現化出来ないそれを、素晴らしい演者の方々に具現化されることによって想像以上のものに感動を覚えることも、もちろん有ります。
けれど、難解な小説のなかに深く沈みこみ、その人物の感情を追いかけるように読むと、重苦しい、言葉にすることなど到底できそうにも無い感情が伝わってくるような呼吸音が聴こえてくるように思ってしまう。
そんな風に、錯覚させる力が、古典、特にドフトエフスキーには感じられてしまう、と筆者は述べています。
この、「行間を読む」という行動。
小説の問題を解くテクニックにも使えるものなのですが、何故登場人物がそんな行動を取ってしまったのか。
それは、文章に書かれていることは殆どありません。
書かれていることではなく、その間。書かれていないことに、真理が潜んでいる。それを探るために、知るためには、あちらこちらにヒントが沢山隠れています。
言葉を躊躇ったのは、何故なのか。
言いたいことはあるのに、言えないのは何故なのか。
その理由は文章で書かれていることは有りません。その理由が深刻なものであれば、大事なものであればある程、人は口をつぐみます。
だから、その理由が読みながら伝わってくるようになると、その世界に引き込まれてしまう。
その人物のことを、もっと理解したい。どうしてこんなことをしたのかを考え、感じ、思考を巡らすことによって、見えるものが、分かることがある。
そして、それは大抵、「書かれていない」のです。
沈黙が、最高の表現方法である、という筆者の主張とも繋がる部分があります。
言えば良いのに、何故そこで言葉を止めるのか。
その理由が解らない。謎があるからこそ、人はその物語に惹かれるのです。
そして、それは、人が黙る。沈黙するのは、何かしらの理由があるからだと私たちが無意識に知っているからなのでしょう。
だから、その理由を知りたいと思う。知りたい衝動が、その呼吸音を。のどの奥の沸騰音を、読みながら「聴かせる」のです。
-犬の悲しみの真実-
犬のグルグルは、そもそも言葉を持たないのだから、訥音とはいいかねる。永遠に語らぬ者のみが表しうる悲しみの色が眼ににじむだけだ。(本文より)
はい、ラストの文です。
犬は喋らないのだから、訥音とは言えないけれど、大抵犬って、何かを訴えて、しきりに要求するのにそれが伝わらないんだ、と成ると、しゅん……と耳を垂れて、項垂れますよね。
明らかに、「ああ、分かってもらえないんだ……」っていう雰囲気で、「くぅん」って鳴いたりする。
その、犬が本来伝えたかったことは全く私たちには分かりませんが、不思議と、その項垂れた瞬間の「ああ、伝わらないんだ……」という、絶望にも似た感情は伝わってきますよね。(笑)
それだけは伝わってくる。
具体的なものは一切分からないのに、伝わらないことを残念に思っている感情は、その目ににじむ悲しみや、うなだれる雰囲気から強烈に感じることができるのです。
それを思うと、言葉よりも、それ以外のものがどれほど雄弁にその人の心を写しているのかが、良く解ります。この場合は、犬ですが(笑)
沈黙が最も伝達力の強い、表現方法である。
「ない」ことが、「ある」ことよりも強い影響力を持っている。
芸術論の、基本的な考え方なのかもしれませんね。
(参照⇒ミロのヴィーナス 解説その6 まとめ)
【まとめ】
ドフトエフスキーの小説を例示に出し、「書いていない」行間に、その人物の心の揺れや葛藤。悲しみの深さや、苦しみの度合いが滲みでている。
そのような、呼吸音を「聴いて」しまう。
ある意味では、具体的に書いていないことによって、人の想像力をかきたたせ、謎があるからこそ書いていない部分を想像し、その間を埋めようとする。
それは、空白があるからこそ、です。
沈黙があるからこそ、何故その人は沈黙しているのか。その理由を人は考え、分かろうとする。
それが、沈黙が最も表現力の強い表現方法である、という筆者の主張の根拠です。
では、明日は全体のまとめです。
ここまで読んで頂いてありがとうございました。
「無い」ことの価値を、少しだけ頭のなかに入れておいてください。
続きはこちら⇒声の諸相 解説その5 まとめ



コメント