今回は、下人に訪れる、ある切っ掛けを解説していきます。
この、偶然出会った「切っ掛け」とも言える出来事で、下人の行動は羅生門の下で座り込んでいた時とは、全く別の雰囲気を醸し出すようになります。
【前回のまとめ】
-不安定な精神で衝撃的な出来事を見る下人-
精神的に不安定、とはよく言いますが、これはどういうことなのか。
自分で自分の行動がコントロールできない状況、ということになります。そして、その不安定さがまた、精神的な混乱を招く。
悪循環の時に、さらに衝撃的な出来事が起こった時に、普通の、平均的な人間である下人は何をしてしまうのか。
では、続きを読んでいきましょう。

皆、大好きですよね。「正義」と言う、言葉。
【第13段落~第16段落】
-生きている人間よりも死体を選ぶ下人-
さて、この八方ふさがりだった下人が出会うものがあります。その切っ掛けは雨が全く止まず、寒さもきつくなってきた状態で、風邪をひかないために、せめて少しでも雨をしのげるところ。人目を避けられるところで寝たいと思ったところから始まりました。
雨は、まだ解ります。
けれど、人の目を避けたいのは、何故なのか。
むしろ、職を得るにしろ、下人が否定している盗みを働くにしろ、人に出会わなければ話は始まらないのに、下人はそれを避けています。
誰かに見つかったら、怒られると思っているのか、それとも
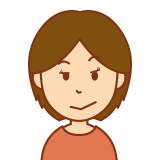
「この人、何?」
と不審そうな視線で見られるのが嫌だったからなのか……
よほど酷い目に逢ってきたのかなと、ちょっと考えてしまいます。
その下人が、人目を避けるように昇ったのは、羅生門の上です。楼閣の部分に繋がる階段を昇り、ここならばどうせ人がいても、あるのは死体だけ……
ちょっと待ってください。
リアルに考えてください。
どう考えても、生きている人間がいる場所の方が落ち着けると思うのですが、今の下人には生きている人間の方が怖かった。
無防備な姿をさらしたら、身ぐるみ剥がされるか、殺されるか。少なくとも助けてくれる人はおらず、危害を加える人間だけが存在すると下人は思い込んでいたわけです。
死人は、何もできません。
なら、その方が良いと思える精神状態。更に死体の山の中で寝ようとする気持ち。
まともでない事は、確かです。
恐怖と不安、それから人に対する潜在的な拒否感。それらがないまぜになって、死体の山でも、何もせずに無事に眠れるなら、それでいいやと思えてしまう。
さらっ、と書いてありますが、恐ろしい状態であることが、読み取れます。
-下人は太刀を持っていた-
階段をのぼりながら下人は腰に下げた太刀を落とさないように気をつけます。
ここから、下人の仕事は、貴族のボディガードや用心棒。少なくとも、刀を必要とする職業だったの可能性があります。
検非違使(当時の警察みたいなもの)とまではいかずとも、太刀を持っているということは、この時代結構特殊です。武士が台頭する時代ではありませんが、太刀を必要とする職種だった。
今で言うと、警備員でしょうか。
要するに、太刀の使い方を知っていた。
それを取り扱う技術も持っていたことも、同じく情報として貴重なものです。
武器は使い方を知っていて、初めて使えるものです。下人には、その知識が少なくともあったとみなして良いでしょう。
-下人が目撃したもの-
楼閣の上にあったものは、死骸の山でした。
かつて、生きていた人間だとは思えないほどに、人形のように積み上げられた夥しい死体の山。当然、死臭が漂っています。
人の腐乱した、つまり腐った人間の臭いはとんでもない悪臭だと言いますが、一瞬鼻を覆った下人も、なぜか次の瞬間から鼻を覆う事をやめてしまいます。
しかし、その手は、次の瞬間には、もう鼻を覆う事を忘れていた。ある強い感情が、ほとんどことごとくこの男の嗅覚を奪ってしまったからである。(本文)
下人の目に、一人の老婆の姿が映ります。その老婆が死体の山の中を、何かを確認するように歩いている。まるで、品定めでもするように、死骸を眺めている。
下人は、六分の恐怖と四分の好奇心とに動かされて、暫時は息をするのさえ忘れていた。(本文)
強い感情、とは、恐怖と好奇心です。
ホラー映画を観たい心境だと思ってください。
怖いけど、見たい。知りたい。
人は、知らないものに恐怖を抱くと言います。知らないからこそ、正体を知って安心したい。その衝動から、見たくなる。確かめたくなる。
その老婆は、女の死骸を見つけると、髪を抜いていきます。
手で髪を梳くように、抜き始める。
その行動を観察していると、下人にある変化が訪れます。
-感情の変化をとらえる-
この移り変わりを追いかけているのが、問題と言っていもいいほどです。
下人の恐怖と好奇心は、老婆の行動の意味を見たい、知りたいという好奇心が満足するにつれ、正体が解ったことに比例するように恐怖も去っていき、代わりに違うものがこみ上げてきます。
ここをしっかりと押さえること。
感情が抜けていくのは、満足するからです。
満足する、何かしらの原因があるので、そこをしっかりとチェック。
そして、抜けて行った感情の隙間を埋めるように、下人の心にある感情が芽生えます。
そうして、それと同時に、この老婆に対する激しい憎悪が少しずつ動いてきた。(本文)
そう。憎悪。この老婆を憎む気持ちが芽生えてきたのです。
むしろ、あらゆる悪に対する反感が、一分ごとに強さを増してきたのである。(本文)
何故、ここまで下人の感情は激しく揺れたのでしょうか。
極端すぎる感情のぶれは、どうして起こったのか。
-人は絶対的に正しい立場にいると錯覚して、人を非難する-
この下人と老婆の違いはなんでしょうか?
年齢や性別などを全く除外して、行動のみで捉えるのならば、
下人⇒見ているだけ。
老婆⇒死人から髪を抜いている。
という事になります。それだけで、何故老婆を憎めるのか。
とても不思議なのですが、この下人の事をもう一度考えてみましょう。
人は、両極端に考えが振りきれる、といいます。
という事です。
ここで言うのならば、下人は老婆を見た瞬間。
極度の恐怖と好奇心に、嗅覚すら奪われています。悪臭を除外する恐怖ってどれほどでしょうか?少なくとも、感覚の一つを遮断できるほどですから、よほどのショックであったことは想像が付きます。(生ごみの臭いの中で、それを忘れられるほどの恐怖、と考えると想像しやすいかと)
そうして、不安定な状況に陥った下人は、老婆の行動に
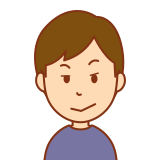
「なんてことをしているのだ!」
と憤ります。
事情も何も聞いていない。
究極の自己中心的な正義感です。判断基準は自分であり、更に不安定な精神状態であるからこそ、その憎悪も酷くなる。
対象を悪だとするのならば、己の立場はその真反対の正義でなければなりません。
悪いことをしているという自覚があって、悪行をしていることなどありえません。そして、被害も受けていないのに、一方的に誰かを批判する時は、大抵そこには身勝手な自己中心的な思い込みが作用しています。
これに囚われてしまうと、人は何を行ってしまうのか。
【今日のまとめ】
-不安定な状況は極端な行動に出やすい-
好奇心と恐怖から、老婆を憎悪するまでに至った、下人の心。
この間、下人は老婆と一言も話していません。人は、何も話さなくとも人を恨めるのです。なぜ、そこまで極端な心の変化があったのか。
下人は普通の人間です。凶悪犯でも、凶悪な意志を持っている危険人物でもない。
だからこそ、怖いのです。
-人は自分が正しいと思い込んだ時に、とんでもないことをする-
人は、自分が間違っていると思うことは、ほとんどありません。
自分が正しいと思い込んでいるとき、人は残虐なことをする。性格や、それ以前の語っていた言葉をすべて忘れて、自分の行動を正当化します。
さて、この後、下人は老婆に対して何をしてしまうのか。
続きはまた明日。




コメント